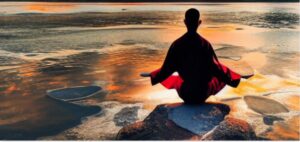即身仏(即身仏)とは何か?生きながら仏となる修行の意味・目的・方法・歴史・現代の信仰までを、史料とともにわかりやすく解説します。祈りと信仰の文化を今に伝える。
即身仏とは?意味と定義をわかりやすく解説
即身仏(そくしんぶつ)とは、仏教の修行者が生きたままの肉体で悟りを得て仏となることを目指した信仰・行法です。
死後も人々を救い続ける存在になるため、自らの身体を供養の対象としたものを指します。
日本では主に真言密教や修験道の流れを受け継ぎ、東北地方を中心に実践されました。
「即身仏」とは「生きながら仏になる」こと
「即身仏(そくしんぶつ)」という言葉を直訳すると、「この身のままで(即)仏になる(身仏)」という意味になります。
仏教では一般的に、修行の果てに死後悟りを得て仏となると考えられています。
しかし即身仏は、「生きながらにして成仏を実現する」という極めて珍しい思想に基づいています。
この考えは、真言宗の開祖・空海(弘法大師)が説いた「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」に由来し、
修行によって心身が一体となり、今この瞬間に悟りへ到達できるという教えが根底にあります。
「この身このまま仏なり」— 空海『即身成仏義』
ただし、後世における「即身仏」は、単なる思想ではなく、
実際に肉体を保存し、祀られる物理的な存在として現れた点が特徴です
「即身成仏」と「即身仏」の違い
| 用語 | 読み | 意味 | 形態 |
|---|---|---|---|
| 即身成仏 | そくしんじょうぶつ | 修行によって生きながら悟りを得る思想 | 教義・理念 |
| 即身仏 | そくしんぶつ | 肉体を残して仏となる修行者 | 実践・現象 |
「即身成仏」は心の修行、
「即身仏」はその修行を肉体で具現化した結果といえます。
つまり、即身仏とは“生きた教義の結晶”であり、
仏の世界を現世に体現しようとした行為でもあります。
どのような宗派・地域で行われたのか
即身仏の修行は、密教・修験道・山岳信仰の影響が強い地域で行われました。
主な宗派・地域は以下の通りです:
| 地域 | 宗派・背景 | 特徴 |
|---|---|---|
| 山形県・新潟県 | 真言宗・修験道系 | 湯殿山信仰、自然乾燥条件が良い |
| 富山・長野・秋田 | 山岳修行・修験道 | 霊山での入定信仰 |
| 高野山・四国 | 真言宗 | 理念的には即身成仏思想を継承 |
特に山形県の湯殿山系統(出羽三山信仰)では、多くの修行僧が即身仏として祀られ、
今日も寺院でその姿を見ることができます(例:南岳坊・海向寺など)。
>>即身仏の見られるお寺まとめ
即身仏は“死”ではなく“祈り”
現代の視点から見ると、即身仏は「生き埋め」や「自死」に近い印象を持たれがちです。
しかし、信仰の文脈では**自己犠牲ではなく“祈りの延長”とされます。
修行僧たちは自らの肉体を仏に捧げ、
「この世の災厄を自分が引き受ける」という慈悲の心から入定したのです。
「自らをもって衆生を救う」
修験道口伝より
この行為は、自己を滅するためではなく、永遠に他者のために祈り続けるための“変身”でもありました。
現代に伝わる「即身仏」の意義
現代では新たな即身仏修行は行われていませんが、その精神は今も多くの寺院や信仰者に受け継がれています。
即身仏は、単なる宗教的現象ではなく、人が「死を超えて何を残すか」を問い続けた文化遺産といえます。
今も祀られている即身仏の姿は、「命を超えた祈り」と「生の覚悟」の象徴として、訪れる人々に深い静寂をもたらします。
日本現存即身仏18体・完全リストとマップ
日本国内に現存し、学術的・文化的に確認されている即身仏は全18体です。そのうち半数近い8体が山形県に、4体が新潟県に集中しています。
| エリア | 寺院名 | 即身仏名 | 拝観 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県 鶴岡市 | 注連寺 | 鉄門海上人 | 可 | 左眼を捧げた伝説・小説『月山』舞台 |
| 山形県 鶴岡市 | 大日坊 | 真如海上人 | 可 | 96歳まで生きた長寿の上人 |
| 山形県 鶴岡市 | 本明寺 | 本明海上人 | 可 | 庄内地方で最も古い即身仏 |
| 山形県 鶴岡市 | 南岳寺 | 鉄竜海上人 | 可 | 鉄門海の弟子・山形県内では最後に入定 |
| 山形県 酒田市 | 海向寺 | 忠海上人 | 可 | 日本で唯一2体が並ぶ寺院 |
| 山形県 酒田市 | 海向寺 | 円明海上人 | 可 | 忠海上人とともに並んで安置されている |
| 山形県 白鷹町 | 蔵高院 | 光明海上人 | 可 | 民家のような寺院で拝観できる |
| 山形県 米沢市 | 明寿院 | 明海上人 | 可 | 衣装が色鮮やかに残っている |
| 新潟県 長岡市 | 西生寺 | 弘智法印 | 可 | 日本最古(600年以上前・1363年) |
| 新潟県 村上市 | 観音寺 | 仏海上人 | 可 | 日本最後(明治36年入定) |
| 新潟県 村上市 | 観音寺 | 全海法師 | 年1回 | 毎年7月8日のみ御開帳される |
| 新潟県 柏崎市 | 真珠院 | 秀快上人 | 非公開 | 一般公開はされていない |
| 岐阜県 揖斐郡 | 横蔵寺 | 妙心法師 | 可 | 遺体の保存状態が極めて良好 |
| 神奈川県 横浜市 | 總持寺 | 石頭希遷 | 可 | 中国(唐代)の禅僧のミイラ |
| 福島県 石川郡 | 貫秀寺 | 宥貞法印 | 可 | 薬師堂にて拝観可能 |
| 茨城県 桜川市 | 妙法寺 | 舜義上人 | 可 | 関東で拝観できる貴重な即身仏 |
| 長野県 阿南町 | 瑞光院 | 心宗行順 | 可 | 「行人様」として親しまれている |
| 京都府 京都市 | 阿弥陀寺 | 弾誓上人 | 非公開 | 石棺の中に安置されている |
なぜ山形県に「即身仏」が多いのか?歴史と信仰背景
日本全国に現存する即身仏は18体ですが、そのうちの約半数にあたる8体が山形県(庄内地方)に集中しています。また、新潟県にも4体が存在します。
なぜ、東北のこの地に即身仏信仰が根付いたのでしょうか?その背景には、平安時代から続く「出羽三山(でわさんざん)」の山岳信仰と、真言宗の開祖・空海(弘法大師)の教えが深く関わっています。
出羽三山と「生まれ変わり」の修行
山形県の出羽三山(羽黒山・月山・湯殿山)は、古くから修験道の聖地でした。それぞれの山は以下の時間を象徴しているとされています。
- 羽黒山(現在):現世の幸せを願う
- 月山(過去):死後の世界・祖霊が鎮まる場所
- 湯殿山(未来):新しい生命をいただく「再生」の場所
特に「湯殿山(ゆどのさん)」は、この世ならざる聖域とされ、即身仏を目指す行者たちが最後に目指した場所でした。厳しい自然環境の中で自らを極限まで追い込む修行は、単なる苦行ではなく、古い自分を捨てて「仏として生まれ変わる」ための儀式でもあったのです。
空海と「海」の字を持つ行者たち
即身仏の名前を見ると、「鉄門海」「真如海」「本明海」など、多くの方の名前に「海」の字が入っていることに気づきます。
これは、即身仏の思想的基盤を作った弘法大師・空海にあやかっているためです。空海は「即身成仏(生きたまま仏になる)」という教えを説きましたが、山形の行者たちはその教えを自らの肉体を使って実践し、民衆の苦しみを救おうとしました。
この歴史的背景を知ると、即身仏が単なる「ミイラ」ではなく、地域の人々を救うために命を捧げた「祈りの姿」であることがより深く理解できるはずです。
即身仏の目的は「衆生(しゅじょう=すべての人々)を救う」こと。 それは、死後に成仏するのではなく、生きたまま人々の苦しみを背負い、永遠に祈り続ける存在になることを意味しました。 自らの命を供養とし、慈悲と覚悟の象徴として入定したのです。即身仏の根底にある「衆生救済(しゅじょうくさい)」の願い
仏教では、修行者の最終目的は「悟り」ではなく、すべての生きとし生けるものを救うことにあります。
即身仏となった僧侶たちは、この教えを最も直接的な形で実践しました。
「自らの身をもって衆生を救う」—— 修験道古伝
即身仏は、自分の命を犠牲にして人々の病や飢え、災厄を引き受け、その代わりに村や地域の平安を祈願する“永遠の供養者”となることを目的としていました。
こうした信仰は、特に自然災害や飢饉が多かった東北・北陸地方で強く根付いたといわれています。
僧侶が自らを「地域の守り神」として捧げることで、人々に希望をもたらしたのです。
「死を超えて祈る」——即身仏の思想的背景
即身仏になる行為は、仏教における「死」の概念を超えた実践でした。
彼らにとって死は終わりではなく、祈りの永続化を意味していました。
真言密教や修験道では、人間の身体そのものを「仏の器」と捉え、肉体を極限まで浄化することで、仏の領域に近づけると信じられていました。
この発想は、「即身成仏(この身で悟りを得る)」の思想に基づいており、死後に成仏を待つのではなく、今この身体で仏になることが最上の修行とされたのです。
「身口意を清め、この身をもって仏となる」
空海『即身成仏義』
自殺や殉教との違い
現代の価値観から見ると、即身仏の行為は「自ら死を選ぶこと」と誤解されることがあります。
しかし、宗教的にはそれは自死ではなく供養行為でした。
即身仏は、「死ぬための修行」ではなく「生きて仏になる修行」です。
肉体を滅ぼすことが目的ではなく、祈りと信仰を永続させるための手段でした。
彼らは死を恐れるどころか、死をも修行の一部として受け入れる覚悟を持っていたのです。
つまり、即身仏は命を捨てるのではなく、命そのものを仏道に捧げるという宗教的転化を遂げた存在でした。

地域社会の中で果たした役割
江戸期の日本では、飢饉や疫病が頻発し、人々は不安定な生活を強いられていました。
そんな時代背景の中で、即身仏の修行僧は**“村を守るための祈り人”**としての役割を担いました。
村人たちは、即身仏になった僧を「御身仏さま(おみほとけさま)」と呼び、
祈願・豊作・病気平癒などの守護仏として崇めてきました。
この信仰は、寺院単位ではなく地域共同体の祈りの中心となり、
今でも山形県や新潟県の寺院では、年に一度の供養祭が続いています。
現代における「即身仏の精神」
現代において、即身仏のような修行は行われていません。
しかし、その**「他者のために祈り続ける心」**は、僧侶や一般信者の中に今も受け継がれています。
社会の中で自分を律し、誰かの幸せを願って生きること——
それは、現代における“即身仏の形”とも言えるでしょう。
即身仏は、極限の宗教行為であると同時に、
人間の「他者への思いやり」という根源的な感情の表れでもあるのです。
即身仏になるまでの修行と工程
即身仏になるための修行は、十数年にも及ぶ極めて厳しい行法です。
修行者は食事・呼吸・肉体を制御し、心身を極限まで浄化して「朽ちない身体」へと近づけます。
代表的な修行には、木食行(もくじきぎょう)・漆を飲む行法・土中入定(どちゅうにゅうじょう)などがあります。
第一段階|木食行(もくじきぎょう)
修行のはじまりは、木の実・草の根・樹皮など自然のものだけを食べる「木食行」。
米や麦などの五穀を絶ち、動物性の食事も一切摂りません。
これは単なる断食ではなく、体内の脂肪や水分を減らし、
**腐敗を防ぐための“脱水準備”**でもありました。
木食行は通常、数年から10年以上続けられ、
体は痩せ細りながらも、心を鎮め、死への恐れを超越する精神状態を育てます。
「木を食し、心を仏に近づける」
修行口伝
第二段階|五穀断ちと毒飲(漆行)
木食行の後期になると、修行僧は五穀断ちに入り、体を保存するための毒性植物や漆(うるし)を少量ずつ飲みます。
漆の樹液には殺菌・防腐作用があり、体内に取り込むことで死後に肉体が腐敗しにくくなると信じられていました。
現代の科学的見地から見ても、漆の成分(ウルシオール)には防腐性があるため、
この行法は経験的な知恵といえます。
ただし、この修行は極めて危険で、生きたまま中毒死する例も多かったと伝えられています。
「身に漆を入れて、百年に朽ちず」
出羽三山伝承
第三段階|土中入定(どちゅうにゅうじょう)
修行の最終段階が土中入定です。修行僧は、生きたまま地中に埋められ、木の箱や石室に座禅姿で入ります。
その中で鐘や鈴を鳴らし、外の弟子が音を確認しながら祈りを続けます。
鐘の音が止むと、入定が完成した合図とされました。
この行法は、単なる死ではなく、「生を超えた祈りの成就」とみなされていました。
入定後、数年〜数十年が経過してから、弟子たちによって遺体が掘り出されます。
第四段階|掘り出しと即身仏の確認
掘り出された遺体が**腐敗していなければ「即身仏成就」とされ、寺院に祀られます。
遺体が損壊・腐敗していた場合は、丁重に再埋葬され、「成仏に近づいた修行僧」として供養されました。
防腐が成功していた場合は、漆や金箔を塗り、衣を整えて仏像として安置されます。
この過程を「荼毘成仏(だびじょうぶつ)」とも呼びます。
「肉身は滅すれど、法身は常に在す」
湯殿山縁起

修行の期間と環境
即身仏の修行は、最短でも10〜20年、長い場合は30年以上に及ぶこともありました。
特に重要なのは、湿度・温度・土質といった自然条件です。
山形県湯殿山・新潟県村上・富山県立山などは、地下が火山灰土質で湿気が少なく、即身仏が成功しやすい環境だったとされています。
科学的観点から見た「即身仏の成立」
現代の研究では、即身仏は偶然の産物ではなく、経験的な保存技術+宗教的信仰の融合であったと考えられています。
漆・塩・乾燥環境による防腐、加えて山岳の冷涼な気候。これらが重なって、遺体が自然乾燥し、数百年の時を超えて形を保ったのです。
日本の即身仏の歴史と地域分布

即身仏信仰は、平安時代に密教とともに伝わり、室町〜江戸時代にかけて東北・北陸地方を中心に広がりました。
特に山形県・新潟県・富山県などの寒冷乾燥地帯では、信仰と自然条件が重なり、現在も数多くの即身仏が現存しています。
平安時代に芽生えた「生きながら成仏」の思想
即身仏の起源は、平安時代(9世紀頃)に伝わった密教思想にあります。
弘法大師・空海が説いた「即身成仏」という教え――
「この身このままで悟りを得られる」という思想が原点となりました。
この考えがやがて実際の修行行為と結びつき、「現世で悟りを形にする」という実践的な行法として発展します。
当時の日本では、山岳信仰や修験道の盛り上がりもあり、「山に籠もり、身をもって祈る僧」が各地に現れ始めました。
「山は仏のすがたなり」
修験道伝
鎌倉〜室町期|修験道との融合
鎌倉・室町時代になると、密教思想と山岳修行が融合し、**修験道(しゅげんどう)**の中で即身仏の概念が根付いていきます。
修験者たちは、山を神仏の宿る聖地と見なし、苦行を通じて神仏と一体化することを目指しました。
この流れの中で、「自らを仏とし、死後も人々を導く」――という発想が形成され、
のちの即身仏修行の原型となりました。
修験道は山中での断食・瞑想・寒修行などを行う行者(山伏)の宗派で、即身仏修行もその最終段階として位置づけられます。
江戸時代|即身仏信仰の最盛期
江戸中期から後期にかけて、即身仏信仰は最盛期を迎えます。
飢饉・疫病・災害などが相次ぎ、人々は「身をもって救う僧」に希望を託しました。
この時代に入定した即身仏が最も多く、特に出羽三山(山形県)では、湯殿山系の即身仏が数多く誕生しています。
代表的な例には次のようなものがあります:
| 僧名 | 寺院 | 地域 | 時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄門海上人(てつもんかい) | 南岳坊 | 山形県鶴岡市 | 江戸後期 | 飢饉救済を祈願して入定 |
| 真如海上人 | 本明寺 | 山形県酒田市 | 江戸中期 | 海難防止を祈願 |
| 忠海上人 | 海向寺 | 山形県鶴岡市 | 江戸後期 | 湯殿山信仰の中心人物 |
これらの僧侶は、地域の守護仏として現在も祀られ、地元住民の信仰の中心となっています。
「我が身をもって世を救わん」
鉄門海上人遺詞
明治期以降|禁止と文化財としての保存
明治政府の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)運動により、入定行為は「自死」と見なされ、1870年代以降は法律で禁止されました。
しかし、既に祀られていた即身仏は「文化遺産」として保護され、地元の人々の努力によって多くが今日まで保存されています。
現在では、宗教的儀式としての修行は行われていませんが、文化財・信仰対象・観光資源として、即身仏は新たな形で息づいています。
たとえば、山形県海向寺・本明寺・大日坊などでは、定期的に供養祭が行われ、祈りの伝統が守られています。
地域別・現存する主な即身仏
日本国内では、現存が確認されている即身仏は20体前後。
その多くが山形県を中心に、北陸〜東北一帯に集中しています。
| 地域 | 主な寺院 | 即身仏名 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 山形県鶴岡市 | 海向寺 | 忠海上人 | 湯殿山信仰の中心、保存状態良好 |
| 山形県酒田市 | 本明寺 | 真如海上人 | 木食行を重ねた高僧 |
| 山形県鶴岡市 | 南岳坊 | 鉄門海上人 | 飢饉供養、祈願成就伝承 |
| 新潟県村上市 | 西生寺 | 弘智法印 | 北陸唯一の即身仏 |
| 富山県上市町 | 大岩山日石寺 | 快玄上人 | 修験道系、部分的保存 |
即身仏と現代|伝統の継承と学術研究
現代では新たな即身仏修行は行われていませんが、既に祀られている即身仏は文化財・信仰対象・学術研究の三面で大切に守られています。
それは「過去の信仰」ではなく、今を生きる私たちに“祈りと生の意味”を問いかける存在として継承されています。
文化財としての即身仏
明治以降、即身仏修行は法的に禁止されましたが、
すでに祀られていた即身仏は地域文化と歴史の象徴として保存されてきました。
多くの即身仏は寺院で厳重に安置され、
文化財指定や修復を経て、今も人々の信仰の中心にあります。
たとえば:
| 寺院名 | 即身仏名 | 指定・特徴 |
|---|---|---|
| 山形県・海向寺 | 忠海上人 | 鶴岡市重要文化財(1967年指定) |
| 山形県・本明寺 | 真如海上人 | 市指定文化財、定期供養を実施 |
| 新潟県・西生寺 | 弘智法印 | 県指定文化財、北陸唯一の即身仏 |
| 富山県・日石寺 | 快玄上人 | 修験道系、文化的価値高い |
これらの寺では、保存温度・湿度の管理や定期修復が行われ、
遺体そのものを「祈りの遺産」として未来に伝えています。
「祈りのかたちは変われど、即身仏は今も生きている。」
科学的研究による新たな発見
近年では、文化財研究や医学的調査が進み、
即身仏の保存状態や修行方法が科学的に解明されつつあります。
たとえば、山形県教育委員会や東北大学の調査では:
- 肉体の乾燥度合い・ミイラ化の過程が分析され、漆と自然乾燥の複合作用が判明。
- 即身仏の骨格・DNA解析により、実際に高齢まで生きた健康な僧侶が多かったことが確認。
- 内部構造に異物や木材補強が見られないことから、「自然状態での保存」が多いことが明らかになっています。
これらの研究は、信仰と科学の橋渡しとして評価され、国内外の学会でも報告が続いています。
「科学が明らかにするのは構造、信仰が伝えるのは意味である。」
地域と共に生きる“現代の信仰”
現代でも、即身仏は単なる展示物ではなく、「祈りの対象」として多くの人々に支えられています。
特に山形県鶴岡市の海向寺・本明寺では、毎年の「即身仏供養祭」で僧侶と地域住民が祈りを捧げ、
伝統を今に生かしています。
地域では、子どもたちが学校行事で即身仏の歴史を学び、お年寄りは「村を守る御身仏さま」として今も手を合わせています。
現代社会に響く即身仏のメッセージ
現代社会は、豊かでありながら“心の拠り所”を見失いがちです。
即身仏の存在は、生きる意味・祈る意味・他者を想う心を静かに教えてくれます。
彼らの生き方は、苦行や犠牲ではなく、「人のために生きたい」という純粋な願いの形です。
即身仏は、**「生を通じて祈りを成し遂げた人間」**であり、現代の私たちが“本当の豊かさ”を見つめ直す鏡でもあります。
「命とは、誰かのために使うこと。」
現代僧侶の言葉より
即身仏に関するよくある質問
- 現代の法律で即身仏になることはできますか?
-
いいえ、できません。自殺幇助罪(刑法202条)や死体損壊・遺棄罪(刑法190条)に抵触するため、現代日本で即身仏の修行を行うことは禁止されています。
- 即身仏とミイラの違いは何ですか?
-
一般的なミイラは死後に内臓を取り出すなどの人工処理を行いますが、即身仏は生前の過酷な修行(木食行)によって体内から脂肪や水分を抜き、生きたまま土に入る点が異なります。
| 比較項目 | 即身仏 (Sokushinbutsu) | 一般的なミイラ (Mummy) |
| 動機 | 衆生救済(他人のため) | 自身の復活(自分のため) |
| 処理の時期 | 生前から開始(木食行) | 死後に人工処理 |
| 内臓 | あり(体内に残る) | なし(壺などに保管) |
| 脳 | あり | 鼻から掻き出す |
即身仏にもっと詳しくなるための4つの真実
即身仏の歴史や意味について解説してきましたが、修行の裏側にはさらに興味深い(そして恐ろしい)真実が存在します。当サイトでよく読まれているトピックを紹介します。
① 修行に失敗するとどうなるのか?
即身仏になるための修行は過酷を極めます。土中入定ののち、残念ながら即身仏になれなかった僧侶はどう扱われたのでしょうか。また、失敗例とされる画像や処刑説の真相について解説します。
② 究極の疑問「トイレ」はどうしていた?
木食行を行い、土の中に入る直前、僧侶たちは生理現象とどう向き合っていたのでしょうか。肛門に栓をするという説や、医学的な観点からの「排泄の限界」について検証します。
③ 「即身仏」と「ミイラ」の決定的な違い
「腐らない死体」という意味では同じに見えますが、その製造工程と精神性には天と地ほどの差があります。人工的に作られるエジプトのミイラと、自らの意志で仏になる即身仏の違いを比較します。
【保存版】全国の即身仏に会いに行く
現在、日本国内で拝観可能な即身仏は限られています。現存する18体の即身仏がどこのお寺に祀られているのか、拝観情報や場所を網羅したデータベースです。
筆者の考察とまとめ
筆者の考察とまとめです。即身仏とは、ただ肉体を保存した僧侶の遺体ではない。それは、人間が「祈り」や「慈悲」といった目に見えないものを、命そのもので形にしようとした行為の結晶である。
彼らは死を恐れたのではなく、死を超えて祈りを続けるために生き抜いた人々だった。
その行為は自己犠牲ではなく、人々の苦しみや不安を少しでも軽くしようとした“深い思いやり”の表現だったのだ。
木食行で体を清め、漆を飲み、土の中に座して祈りを捧げる。
そのひとつひとつの行いは、宗教儀式を超えた「人間の覚悟」そのものだ。
彼らは、自らの命を捨てたのではなく、命を仏へと昇華させたのである。
現代を生きる私たちは、科学や合理性によって多くのことを理解できるようになった。
けれど、即身仏の前に立つと、どんな理屈も沈黙し、ただ「祈ることの意味」を感じる。
彼らの姿は、忙しく移ろう日々の中で忘れがちな「静けさ」と「他者への思いやり」を思い出させてくれる。
即身仏は、過去の奇習ではなく、人が“誰かのために生きたい”と願う心の極致だ。
その祈りは、何百年を経た今も、山の霊気の中に、寺院の静寂の中に、確かに息づいている。
「祈りがある限り、即身仏は生きている。」
私たちもまた、日々の小さな行いの中で、誰かを想い、何かを信じ、心を捧げることができる。
それこそが、現代における“即身仏の精神”の継承なのかもしれない。
静かに目を閉じるとき、その祈りは時代を越えて、私たちの中にも灯っている。