即身仏はミイラ宗教・ミイラ仏と呼ばれることがありますが、即身仏とミイラは全く別物です作り方もやり方も異なります。
人間や動物の遺体は、通常であればすぐに腐敗が始まります。なぜ彼らの体は腐ることなく、数百年もの時を超えて現存しているのでしょうか?
本記事では、多くの人が混同しがちな「即身仏とミイラの違い」について、腐らない科学的なメカニズムと、その背景にある歴史や過酷な修行の工程を踏まえて解説します。
ミイラと即身仏はなぜ腐らない?その科学的理由
人間や動物は死亡すると、体内のバクテリアや微生物の働きにより腐敗し、やがて白骨化します。 しかし、ミイラや即身仏は、生前の姿をとどめたまま保存されています。これはなぜでしょうか?
その答えは、腐敗の最大要因である「水分」と「内臓」の処理あります。
腐敗菌が繁殖するためには水分と栄養(内臓や脂肪)が必要です。 ミイラと即身仏は、アプローチこそ違えど、この**「内臓の処理」と「徹底的な乾燥」**を行うことで、科学的に腐敗を止めているのです。
この「内臓をどう処理したか」が、ミイラと即身仏の決定的な違いに繋がります。
ミイラと即身仏の違いを比較
| ミイラ | 即身仏 | |
| 主な保存国 | エジプト | 中国・日本 |
| 保管方法 | 装飾された棺 | 木箱 |
| 保管場所 | ピラミッド 墓地遺跡 | 土中 |
| 内蔵が残っているか | なし | あり |
| なり方 | 死者の遺体を長期保存する。 | 生きたまま入定する。 |
ミイラと聞くとエジプトを思い浮かべる方が多いかと思います、即身仏は中国・日本に多く保存されています。
即身仏は分かりやすいようにミイラと表現され、ミイラと即身仏の見た目を比較するとどちらも綺麗に保存されていたりして、見分けがつかないかもしれません。
しかし、実は「ミイラ」と「即身仏」は大きな違いがあるのです。
その大きな違いは、ミイラ・即身仏のなり方(作り方)になります。
ミイラ:死亡後に長期保存できるように、臓器を取り出すなどの加工を施す。
即身仏:生きたまま土中に埋まり、内臓は取り出さない。内蔵は腐らないように入定前に過酷な絶食を施します。

失敗と恐怖の真実
なぜ彼らは失敗したのか?語り継がれる悲劇と処刑の真実

腐らない科学的仕組
なぜ腐らない?トイレは?科学で解明する即身仏の真実

日本国内の即身仏マップ
全国各地の即身仏全18体・お寺情報のデータベース検索
ミイラの作り方・歴史

ミイラは、死者を蘇生させるという神話的な力を持つと考えられ古代エジプトの王などは、長期保存ができるように腐食を防ぐために保存処理をしています。
人間の脳・内蔵などは水分を多く含んでおり、何も処理せずに保存していると腐り、臭いニオイがし虫などが湧いてしまいます。そのために、ミイラは死亡後に内蔵を取り出しています。
その作り方・手順は諸説ありますが、段々と判明しています。
- 脳の摘出 鼻から機器を使い取り出す
- 内蔵を摘出 切開し胃・腸・肝臓などを取り出す
- 乾燥処理: 体をナトロン(天然の塩化物と炭酸塩の混合物)に浸すなどして、体内の水分を除去します。乾燥は腐敗を防ぐ重要なステップです。
- 包帯や樹脂の使用: 死体を包帯で巻いたり、防腐効果のある樹脂を使用することで、外部からの微生物の侵入を防ぎ、さらに乾燥状態を保ちます。
このように、ミイラは本人が亡くなってしまったあとに他人が遺体を長期保存できるような処理をするのが特徴です。
古代エジプトのミイラ製作では、腐敗を早める内臓を取り除くことが一般的でした。
即身仏の作り方・歴史

即身仏の歴史は空海が始まりと呼ばれており、仏教として日本にも伝わり、全国にも即神仏としてお寺に祀られています。詳しい即身仏の歴史については、下記で紹介しています。
>>即身仏の歴史
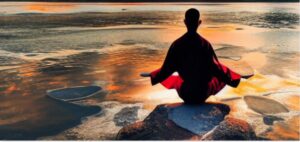
- 厳しい山修行・木のみなどの食事のみに制限し内臓の水分を抜く
即身仏となる僧侶は、生前に極端な食事制限を行い、体内の脂肪と水分を極限まで減少させます。これにより、死後の腐敗が遅れる体質になります。 - 漆の摂取
一部の即身仏の修行では、体内の腐敗を遅らせるために漆の樹液を摂取することがありました。漆に含まれる成分が防腐効果をもたらすと考えられています。 - お経を唱え、土中に入定し適切な保存環境に
死後、即身仏は乾燥した環境に置かれることが多く、これが自然乾燥を促し腐敗を防ぐ助けとなります。
即身仏はミイラと異なり、生きた生身の人間が命を落とした後に腐食せずに長期保存されるように、断食による絶食・水分を徹底的に抜きます。
このミイラと即身仏の違いについては、近年に判明しました。即神仏の解体は許されることでなく、誰もが内蔵が残ったまま絶命していると思っていませんでした。科学の力や過去の歴史書物から即身仏の作り方手順が判明したのです。
まとめ
ミイラと即身仏の見た目は似ていますが、作り方(手順)に大きな違いがありました。
ミイラは死後に防腐処理をしており、即身仏は自らの判断により厳しい修行・断食を行い長期にも身体が残るように生きている段階で用意しています。
現在、日本では即身仏になることは禁止されています。

